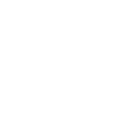みなの衆、耳を貸すがよろし。ウェブカムの灯りの中で、平安貴族のごとく輝く術を伝えたく存じる。まず、衣装は十二単とまでは申さぬが、和風の布を肩にかけるとよろし。カメラの前に立てば、まるで雅な京の都が背後に広がるかの如し。次に、言葉遣いじゃ。現代語ばかりでは味気なし。「わたくし」「ござる」あたりを織り交ぜつつ、ゆったり語れば、見る者もタイムスリップした気分になるやもしれぬ。
さて、動きも大切。扇子を手に持てば、さっと開いて顔を隠す仕草が映える。隠れては見せ、見せては隠れ、これぞ雅の極み。あまり激しく踊れば汗で化粧が崩れるゆえ、静かに優雅にが肝心じゃ。照明はほのかな橙色にして、まるで灯籠の明かりを思わせる風情を出すべし。
とはいえ、あまり古風に寄りすぎると「時代劇の再現か」と笑われかねぬ。適度に現代の軽さを混ぜつつ、京の風情を漂わせるのがコツ。さてさて、この方法でウェブカムの衆目を集められるか、試してみるのも一興ではなかろうか。雅に生きるのも、たまには悪くないぞ。